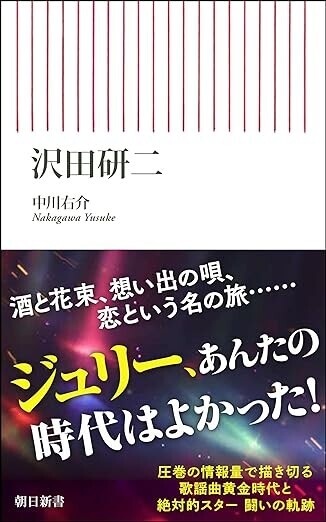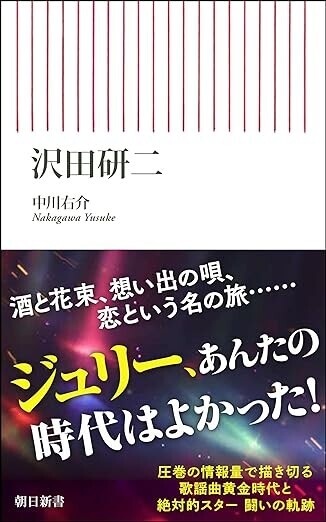
「流し」の中で沢田研二の曲といえば「勝手にしやがれ」「コバルトの季節の中で」「危険なふたり」が人気だ。この間、リクエストで感動したのが、「サムライ」「ヤマトより愛を込めて」「さよならを言う気もない」。そして個人的に大好きなのが、河島英五作の「いくつかの場面」。こころが震える……。
さて、この本。タイトルが素晴らしい。シンプル・イズ・ベスト。スーパースター、沢田研二の生涯がまるごと詰まった本。すばらしい。感動だっ!!!知らないことばかり。
「1966年、京都の若者5人が芸能界にデビュー。沢田研二は、たちまち大スターに。だが、「時代の寵児」であり続けるためには、競争に生き残らなければならない。熾烈なヒットチャート争いと賞レースを、いかに制したか。頂点を極めるまでのジュリーの全軌跡。圧巻の情報量で、歌謡曲黄金時代を描き切る」そのエッセンスを紹介しよう。
・沢田研二は、単に、うまく、カッコいいだけではなかった。男性スポーツ選手、俳優や歌手に憧れ、模倣しようとする。長嶋茂雄、王貞治、石原裕次郎や高倉健が、そういう対象だった。しかし、沢田研二を真似しようとする人は、皆無とは言わないが、ほとんどいなかった。小学生の間で帽子を飛ばすのが流行した程度だ。とても真似できる次元ではなかったのだ。それはファッションや髪型を含めたメイクが奇抜だったということだけではない。真似をすることが許されない、そんな唯一無二の絶対的スターだった。この本はそのスーパースターの奇跡をデータを織り交ぜて描いた歴史物語だ・
・沢田が高校を中退したのは音楽活動をするためではあるのだが、そもそも音楽活動を始めたのは、学校に行かなくなったからだ。京都市立岡崎中学校では野球部に所属し、ファーストを守り、三番か五番を打っていた野球少年だった。入学してみると沢田は授業についていけなくなった。落ちこぼれだったと自叙伝で語っている。行き場がなくなると、空手部にいた同級生が音楽好きだったので、誘われて軽音楽部を見学するようになった。誘われるまま、空手部、軽音楽部、ベラミ、田園へと流れついている。それはまるで天が定めた運命だったかのようだ。
・1948年6月25日鳥取県生まれ。父・沢田松雄が戦中、研究所に勤めていたので「研」、次男なので「二」で研二。戸籍名は「澤田研二」である。
・(井上堯之(当時は井上孝之、1976年のインタビュー)「前列から5、6番目に澤田は据わっていた。「おまえはバンドをやっているのか!?」ステージの上からぼくは沢田に声をかけた。光っていた。持って生まれたスター性が激しくぼくを刺激し、声をかけずにはいられなかった。沢田研二との初めての出会いであった」
・沢田研二の幸運と不運のすべては渡辺プロにあると言っていい。1960年代の芸能界において「ナベプロ帝国」として絶大な権力を持つ芸能事務所に所属していたからこそ、タイガースも沢田研二もスターになれたーこれは事実である。それゆえ実力がありながら、正当な評価を得られなかったのもまた事実だ。渡辺プロは彼らのために資本を投入したが、その何十倍も回収した。見方を変えれば搾取した。それがタイガース崩壊の遠因ともなる。何よりも沢田研二も他のメンバーも団塊の世代特有の反骨精神がありながらも、芸能界最大の事務所の庇護下にあるという矛盾を抱えることになった。
・愛称はどうするか。マネージャーがいくつか言うが、ぴんとこない、そこでジュリー・アンドリュースが好きだったので「ジュリー」としたということになっている。自叙伝によると、ジェリー藤尾が好きだったからとも明かしている。
・マスコミ、つまり「世間の大人」が忌み嫌ったのは、どんなに理屈をこねようが、すでに若くもなければかっこよくもない男たちの、若く美しい青年たちへの嫉妬が根底にある。そうは言えないので「エレキは不良の音楽だ」と主張し、叩き潰そうとした。
・ジャズやロカビリーのブームが終焉した経験を持つ渡辺プロは、GSMブーム終焉の兆しを察し「その後」を見据えていた。極端に言えば、残したいのは沢田ひとりだった。
・沢田研二は音楽を始めたのもバンドに入ったのも、ファニーズへ写ったのも、常に「誰かに誘われた」からで、自ら積極的に道を切り拓いてきたわけではない。しかし、人生の決定的な瞬間においては、絶対に自分の意思を曲げない人でもあった。
・沢田は23歳にして、すでに一度「日本一」を経験していたのだ。自叙伝ではタイガース時代をこう語っている。「タイガースというのは、あれはいわゆる大成功ですよ。まれにみる大成功だと思うんですね」
・沢田研二が他のスターと決定的に違うのは、結婚しても人気が落ちなかっただけではに、結婚した後に頂点を極めた点だ。似た例としては石原裕次郎や木村拓哉もいるが、逆にいうと星の数ほどいるスター、アイドルのなかで数えるほどしかいない。結婚しても人気を保てる自信のある者は少ない。何よりも、それを決断し所属事務所の合意をとりつけるのが困難である。沢田の場合、結婚相手が渡辺プロダクション最大の功労者だったことが、プラスに働いたと言える。渡辺晋と渡辺美佐は伊藤エミの望みを潰すことはできなかった。
・1976年、アルバムのタイトルにもなった『いくつかの場面』は、河島英五の作詞作曲だが、沢田研二の私小説的な詞となっている。「淋しさにふるえていたあの娘」「怒りに顔をひきつらせ去っていったあいつ」「泣きながら抱き合っていたあの人」などが回想され、「できるなら もう一度 僕の回りに集まってきて やさしく肩たたきあい 抱きしめてほしい」とここまでは、誰が歌っても成立する歌詞だった。後半になると「野次と罵声の中で司会者に呼び戻された にがい想い出のある町 有頂天になって歌ったあの町 別れの夜に歌った淋しいあの歌」と、PYG時代のコンサート、あるいはタイガースの最後のコンサートのような光景が歌われる。だが、この曲は沢田サイドの依頼で河島が書いたわけではなく、すでに河島が歌っていたのを沢田が気に入ってアルバムに収録した。レコーディングでは感極まったのか涙声になっている。
・「コバルトの季節の中で」は、TBSの久世光彦が「小谷夏」名義で作詞し、沢田作曲した曲だ。シングルA面を沢田自身が作曲するのは初めてだ。編曲も船山基紀が初めて担った。沢田は自分がシンガーソングライターになることを否定する。「ぼくは自分で自分の歌を作ることに意味をもっていない。その言いのわくの中でぼくのスケールが小さくんるのはいやだ。ぼくは歌っていればいい。だれが作った歌でもよければそれでいい」
・「ぼくの歌は自分の主張とかメッセージとしての歌よりも、ストレートに娯楽としての歌であった。楽しければよかった。そこにジャンル別はない」
・79年沢田研二「レコ大はほしい。だが紅白の大トリはごめんだ」と語っている。「大トリの時は、他の歌手がみんなどっとできて握手したり、声援送ったりするでしょう。ああいうところで歌いたくない。大みそかの紅白は、一年でほんとに最後のしめくくりの歌や。せめてその歌ぐらいは、いつものとおり一人で歌いたいわ」と明かす。
・髪が長いがためにNHKから追放され、識者から理由もなく嘲笑され、誰よりもロックが好きなのにロックファンからは空き缶を投げられ、結婚するとファンから裏切り者と断罪され、下手だと罵られ、男のくせに化粧をしておかしいと言われ、ナチスを美化するのかと批判された歌手は、ついに頂点に立った。(1978年紅白)
・最後にー沢田研二のシングル盤で好きな曲を三つ選べば「危険なふたり」「サムライ」「ヤマトより愛をこめて」だ。明日は違う曲になるかもしれないが」