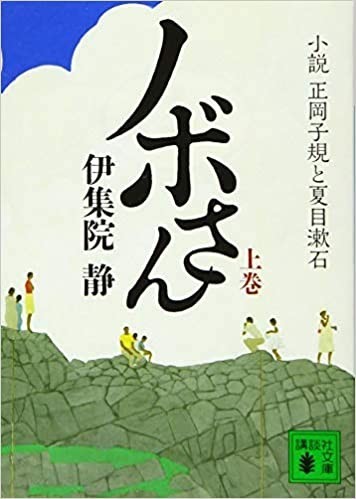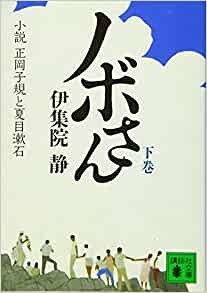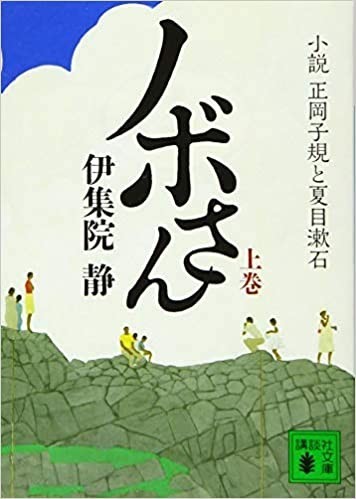
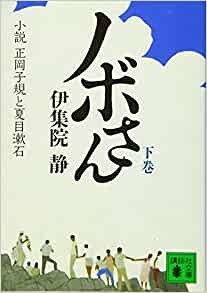
いや〜感動したっ!!!いいなあ!すごいなあ!一気に読み進めてしまった!早くも今年のナンバーワンだろうなあ!!!いままでの正岡子規と夏目漱石のイメージがガチャン!と変わった。すぐに松山に飛びたくなった!(笑)
「ノボさん、ノボさん」「なんぞなもし?」べーすぼーるに熱中し、文芸に命をかけたノボさんは、人々に愛され、人々を愛してやまない希有な人。明治維新によって生まれ変わったこの国で、夢の中を全速力で走り続けた子規の、人間的魅力を余すところなく伝える傑作長編!小説家・伊集院静がデビュー前から温めてきた、正岡子規の青春。俳句、短歌、小説、随筆……日本の新たなる文芸は、子規と漱石の奇跡の出逢いから始まった! 偉大な二人の熱い友情を描いた感動作!」そのエッセンスを紹介しよう。
・子規の投球には、並外れたコントロールがあった。

・一日一句のつもりが子規の頭の中からはどんどん句が出てくる。
・子規には妙に人に好かれるところがあった。一度子規に逢い、
・なにかものにならなくてはならない…。
・この当時、
・松山の時代から、
・「七草集」が七部の巻まで完成すれば、
・

・「“子規”、シ、キ、と読む。時鳥(ほととぎす)のことじゃ。
・子規は「俳書年表」と第して俳諧の歴史を研究しはじめた。同時に「日本人物過去帳」と題していつどんな俳人がいたかをまとめることにした。そうして「俳諧系統」と題し、俳人の系統を一枚の大紙面に罫線を使ってわかりやすく系譜としてまとめたものを作成しはじめた。江戸から明治に時代、国家体制が一変し、それまで武士の隠居した者や町場の商人衆たちのたちのサロン的雰囲気がひろがっていた俳句が時代の変遷で縮小され、その潮流は勢いを失っているためわずかに地方に残る各派の糸をたぐりよせれば案外と用意にはつかめる。
・おそらく明治のこの時期、子規ほおの直感力と能力を持ち合わせた人はいない。時代の中に埋もれ、町衆の遊びとしてかとらえられていなかった俳句を、今日、日本人の文芸のひとつに大きな基軸として成長させたのは、子規の、この一風変わった直感力と、素直に己が愛するものを認め、それをたかめようとする清廉なこころがあったからだろう。
・鳴くならば満月になけほとゝぎす(夏目金之助)
・柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺
・有る程の菊抛げ入れよ棺の中 (大塚楠緒子(くすおこ)の訃報に接した漱石の追悼句)
・当時、編集という仕事はその名称さえないが子規のしていることは現代で言えば、“名編集人”そのものだった。なぜ、こうも編集に才能を発揮できたかを考えると、これは子規の図抜けた記憶力と丁寧(まめと言ってもいい)で執拗とも思われる記録癖である。
・漱石は、現代のわれわれがいうところの「孤独」というものを骨の髄から自覚した最初の日本人であるといってもいい。最高学府で秀才の誉れをほしいままにしても、国の代表として留学しても、結婚して子宝に恵まれても、漱石は孤独だった。そんな彼がほとんど唯一、自分の心を深く知る盟友として認めたのが、子規であった。漱石がロンドンに留学しているあいだに、子規は世を去る。手紙が届くのに一ヶ月以上かかる距離に隔てられた二人が書き送った言葉。
・手紙を読み、手紙を書き、それが終わると二人はじっと闇を見つめ、部屋に座し臥す。近代文学の雄ふたりは、何も灯りが見えない空間でじっと何かをみつめようとしていた。

・漱石は子規の没後、編集を継いだ高浜虚子から乞われ『吾輩は猫である』を『ホトゝギス』に書き、作家としてデビューした。その後の多作ぶりは誰もが知るが、その活躍の期間はわずか十年余りにすぎない。胃潰瘍で血を吐きながら次々と傑作を書きつづけ、『明暗』を完成させることなく亡くなっている。彼もまた血を吐きながら鳴きつづけるホトトギスだったといえるが、そのひたむきな作家人生は、ほかでもない正岡子規から受け継がれたものではないかと思える。今日われわれの前に聳えている豊饒(ほうじょう)な文学の森はまちがいなくその闇の苗床から芽生え育ったものなのである。