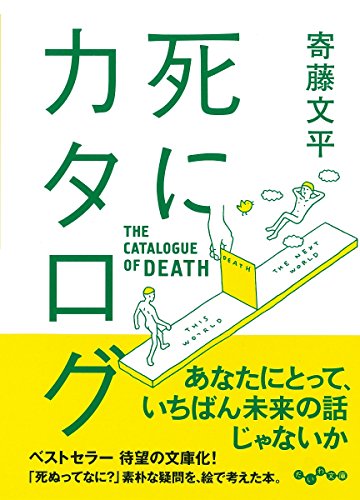毎日毎日、コロナの感染者と死者が報道されているよね。それまでもなくなる方はいたんだろうが、それを知らされることはなかった。それだけ「死」は身近だということ。
そうだよね、死亡率100%なんだから。(笑)
さて、この本。「死んだらコオロギになる。そう信じる人々がいる。あばくのでもなく、かくすのでもなく、寄藤文平が描いた等身大の死のカタチ。「死ぬってなに?」素朴な疑問を、絵で考えた新しい『死の本』」そのエッセンスを紹介しよう。
「死のカタチのキホン」
世の中にある「死のカタチ」をまとめてみると
生きている世界の「コチラ」のほかに
死んだあとの「アチラ」
その2つの世界を「死」という境目が区切っている。
いろいろなカタチで死を考えることができますが、
これを、キホンのカタチとしてみました。
→地底世界に行く[古代日本・五行思想]
今の人は、死んだ人を思うとき、空を見上げたりしますが、
→近所の島に行く[パプアニューギニア・トロブリアンド諸島]
この地域のキリウィナ島の民族は、
・
・「毎日、ちょっとずつ折りたたんでおく」。
「街の年間死亡者数」「家の年間死亡者数」は改めて見ると、コロナで亡くなる人がいかに少ないかがよくわかるよね。「死」について考えよう。オススメです。(・∀・)