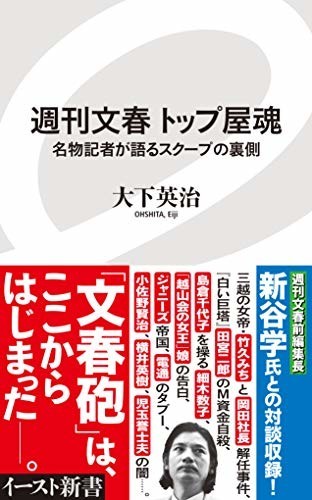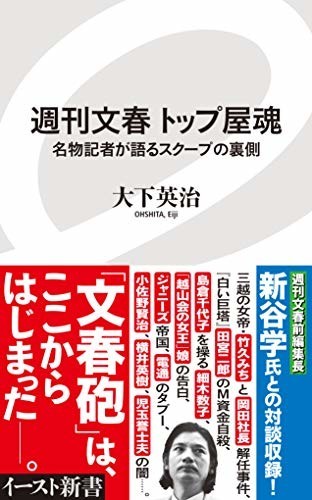
毎日、毎日、コロナ、コロナでそれ以外のニュースがないのが淋しいというか、マンネリというか、つまらないよね。(笑)第一、プロ野球がないんだもんね。スポーツ新聞も週刊誌もネタがないわけだっ!
さてこの本。数々のスクープを連発している週刊文春の記者のハナシ。
「トップ屋」とは、各週刊誌で“巻頭記事”を執筆するフリーのジャーナリストやライターのことで、昭和30年代の週刊誌創刊ブームのころから、そう呼ばれていた。大下は、昭和40年代から50年代にかけて『週刊文春』のトップ屋として多くのスクープを生み出した。本書は、政財界から芸能、闇社会に蠢く“昭和の怪物たち”の裏の顔に鋭く迫った男が、その舞台裏を描いた大作ノンフィクション。社会に激震を与えたスクープはいかにして生み出されたのか?脈々と受け継がれる「文春砲」の秘密がここにある」そのエッセンスを紹介しよう。
・わたしは『週刊文春』では、対象を厳しく切り刻み続けたが、
・テーマはひとつ。それははみ出すエネルギーを描いたことだ。
・さらには、総理大臣を描くにせよ、会社のトップを描くにせよ、
・「なぜ、そんなに取材し、書きつづけるのか。
・わたしはトップ屋となって、「一日五人主義」
・「取材相手が『Aさんは、いい人ですよ』といったら、『
・「取材メモには、まず、取材相手が、自分のことを『おれ』
「なぜ文春は、スクープを連発できるのか」「『週刊新潮』
なーるほど!これはビジネスの世界のインタビューにも使えるねえ。オススメです!(・∀・)