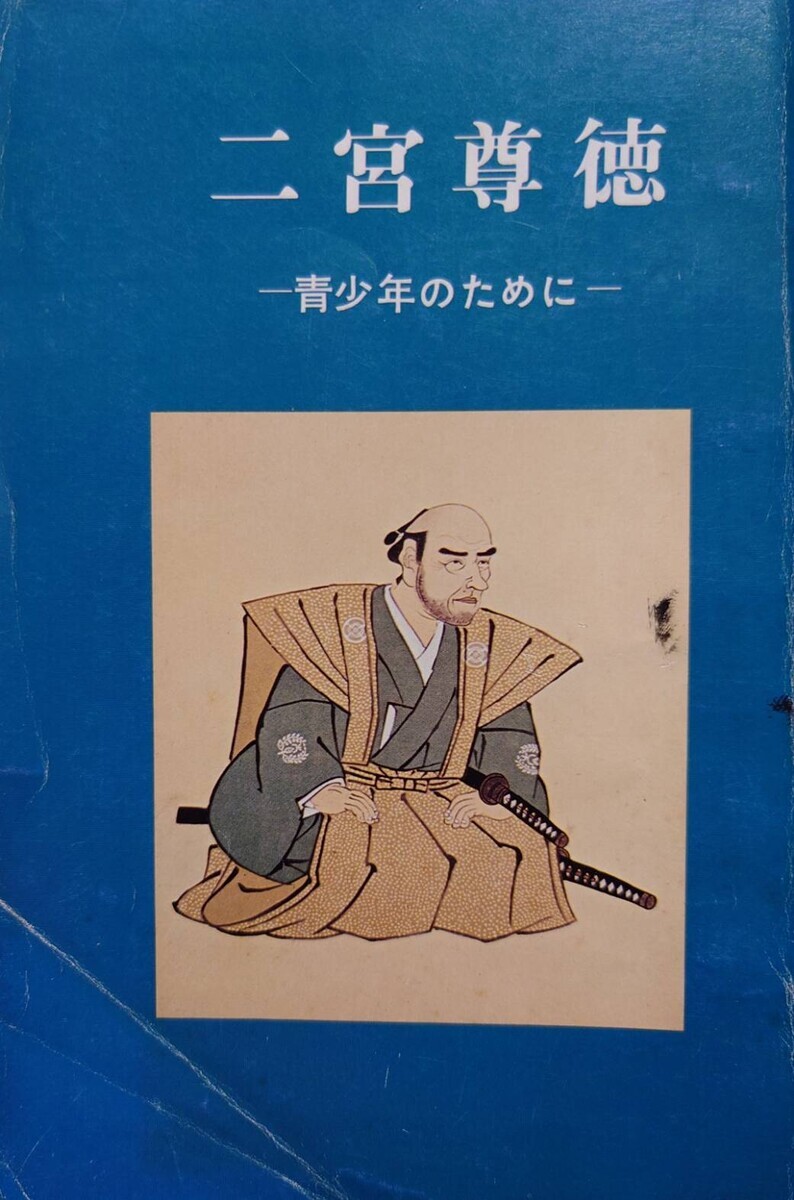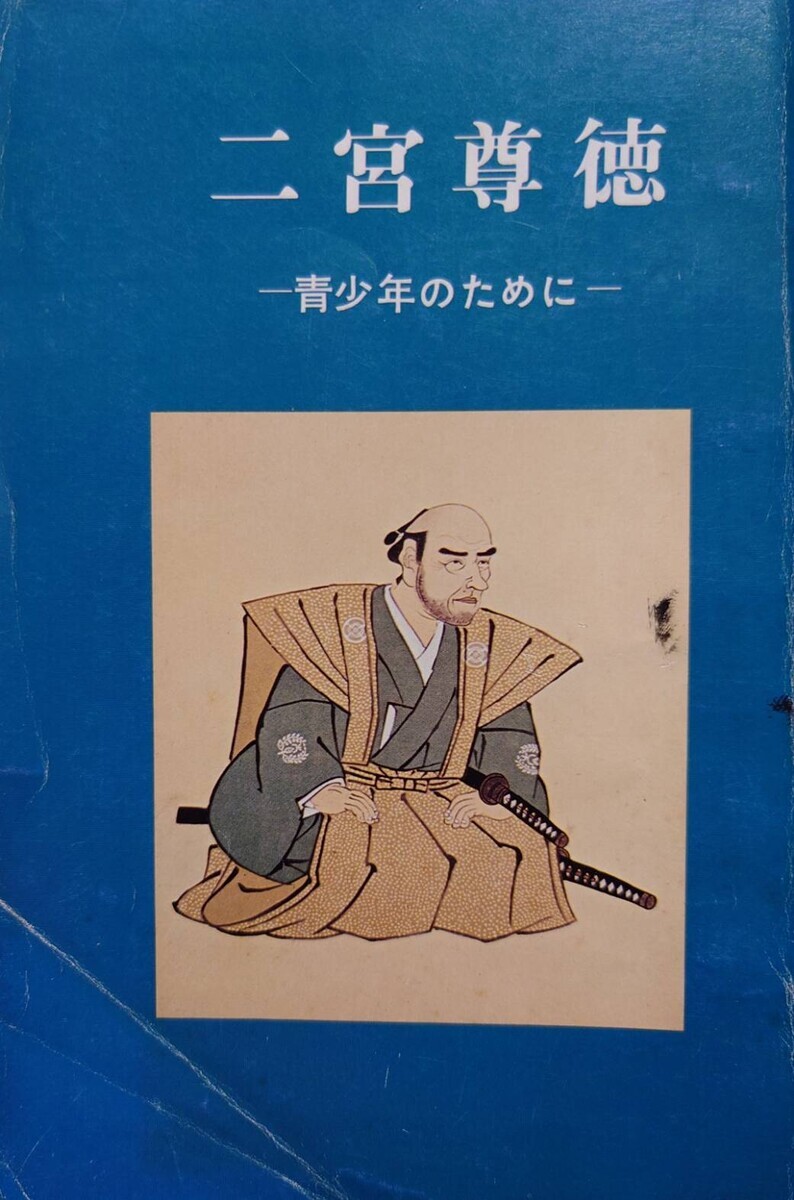
小田原の実家に帰ってきています。本棚が崩れてしまったと母から連絡が。そのハナシを聞いて、ワタシは崩れ落ちました。(笑)片付けていたら出てきたのが、この本。はっきり覚えている桜井小学校5年か6年のときに、二宮尊徳先生の没後120周年祭のために全小中学校に配布されたものだ。
著者の高田稔さんは元白山中学校の校長なんだって。ちょっと読んだらこのページが目に入った。その一部を紹介しよう。
【天道と人道】
徳川時代は、いろいろな道徳や、君と臣の上下関係、
ところが尊徳は、それは別であるといっている。彼によれば、寒さがすぎれば 暑さがくる。夜があければ昼になる。万物が生ずれば、
また、
だから、こうもいっている。「天道に任せれば、堤はくずれ、川は埋まり、橋は朽ち、
また、人間の心のうちにも天道の部分がある。
尊徳はこうして、一方で自然のめぐみを認めながらも、
やっぱり「尊徳」勘定は大事だよね。(笑)やっぱり尊徳先生は偉大だ。非売品だけど、機会があれば手に入れて読んでください。オススメです。(^^)