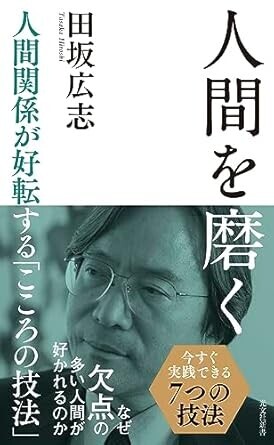
全著作読破を狙っている、田坂広志氏の本。いいんだよね。響くんだよね。説得力があるんだよね〜!♪
「なぜ、欠点の多い人間が好かれるのか? ・「嫌いな人」は、実は自分に似ている ・人間関係がこじれていく「本当の理由」 ・心がぶつかったときこそ、「絆」を深める好機」そのエッセンスを紹介しよう。
・「人間を磨く」という言葉。それは、誰もが惹かれる言葉であろう。「知識とは、風船の如きもの」という比喩がある。「人間関係もまた、風船のごときもの」なのかもしれない。成長すればするほど、人間としてめざすべき高みが見えてきて、自分の未熟さを痛切に感じるようになる。それも、一つの真実なのであろう。
・はたして「人間を磨く」とは「非のない人間」や「欠点のない人間」をめざすことなのだろうか?いや、そうではない。実は、人間は、自分の中に「非」や「欠点」や「未熟さ」を抱えたまま、周りの人々と良き人間関係を築いていくことができるのではないか?その関係を通じて、良き人生を歩めるのではないか?
それは「意思が弱い」からでも「克己心が足りない」からでもある。その真の理由は、我々は「古典」を読むとき、その「読み方」を誤解しているからである。第一の誤解は、古典を読むとき、そこから「人間として、かくあるべし」といった「理想的人間像」を学ぼうとすることである。しかし、むしろ大切なことは「いかにして、人間として成長していくか」という「具体的修行法」を学ぶことである。特に、その修行法の要諦としての「心の置き所」を学ぶことである。
・我々の胸を打つのは、一人の人間としての未熟さと弱さを抱えながらも、ひたすらに人間成長を求めて歩み続けた、。その姿であり、自身の歩みの遅さに、ときに天を仰ぎ、溜め息をつきながらも、決して、その歩みをやめなかった、その姿である。
・第三の誤解は、何か?
自分の中に「統一的人格」ではなく「様々な人格」を育てることである。実は、我々の中には「幾つもの人格」があり、仕事や生活の場面や状況に応じて、我々は、それらの人格の使い分けを、処している。めざすべきは、自分の中の「幾つもの人格」を見出し、育てることであり、それらの人格を、仕事や生活の場面や状況に応じて、適切に切り替える能力を磨くことである。自分の中の「鬼」や「悪」と呼ぶべき部分から目を背けることなく、その存在を認めつつ、それらの人格を御していくことのできる「もう一つの人格」を育てていくことである。
・第三の誤解は、何か?
自分の中に「統一的人格」ではなく「様々な人格」を育てることである。実は、我々の中には「幾つもの人格」があり、仕事や生活の場面や状況に応じて、我々は、それらの人格の使い分けを、処している。めざすべきは、自分の中の「幾つもの人格」を見出し、育てることであり、それらの人格を、仕事や生活の場面や状況に応じて、適切に切り替える能力を磨くことである。自分の中の「鬼」や「悪」と呼ぶべき部分から目を背けることなく、その存在を認めつつ、それらの人格を御していくことのできる「もう一つの人格」を育てていくことである。
いいなあ。田坂さんの文章は、単なる自己啓発的な言葉じゃない。科学者としての説得力があるよなー。いいなあ。オススメです。(^o^)
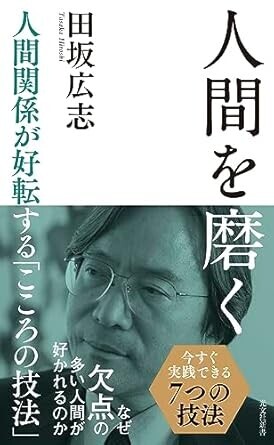
他のこれらの本もオススメです。
