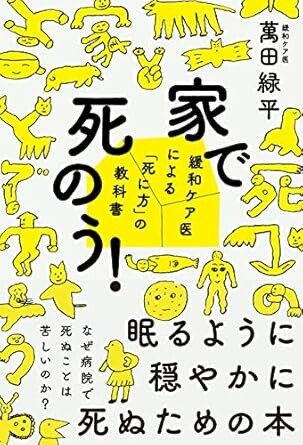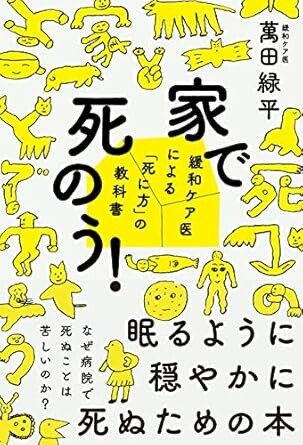
父が自宅で亡くなって20年。父方の祖母も、母方の祖母も小田原の自宅で亡くなった。義姉も真鶴の自宅で亡くなった。あれっ!?小野塚家って、みんな自宅で亡くなってるわー!♪ ワタシが生まれたのも、新潟の自宅だったし。そうかあ!あまり病院に縁がないんだなー!(笑)(=^・^=)
「眠るように穏やかに死ぬための本――なぜ病院で死ぬことは苦しいのか?」そのエッセンスを紹介しよう。
・すでに死が近い終末期にもかかわらず、
・つらく悲しい死の現場に何度も接するにつれ、
・私は14年前から「在宅緩和ケア」を自らの専門とし、
・私の在宅緩和ケアの現場では、病院で治療をやめたり、
・私は病院医療と在宅緩和ケアの両方を見てきた立場として、
・人は誰もが死にます。だんだん元気がなくなり、だんだん食事がとれなくなり、
・なぜ、病院で死ぬのは苦しいのか?死そのものは本来、
・「病院で治療をやめる」ということは、「死を認める」
・在宅緩和ケアを選択し、
・たとえば、薄毛になる、白髪になるのは病気でしょうか? 違います。老化です。老眼や白内障になることも、
・これらと同じで、心臓の老化が進めば心臓病と言われ、
・老化のスピードは人それぞれ、臓器それぞれです。
・顔や性格が違うのと同じで、臓器(脳、内臓、髪、目、皮膚、
・若くして病気になってしまう人は、
・つまり、「病気」というのは、ふつうの人よりも、
・人間は医療の進化のおかげで認知症になるまで(
・人間はいったい、どこに向かおうとしているのでしょうか。
これなどは、「病気はただの老化」
・ 喫煙習慣がある人は、10~
・腎臓が機能しなくなると、人は死にます。しかし現在、
・若いころから発症する病気について、「それは老化です」
・比較的若い時期に発症する難病として「リウマチ」があります。
・認知症は恐ろしい病気ではなく、医療によって「作られた状態」
・死者を出してはいけない、高齢者でも死んだらダメ、
外科医時代、手術が必要になると、私は患者さんの肺機能、
・自宅で最期を迎える患者さんには、何か劇的な変化(急変)が起こることはなく、しだいに食べられなくなり、歩けなくなり、
・在宅緩和ケアの門を叩いた当人や家族に、
・医師が患者さんに治療を勧めるときの定番フレーズが「
・そして、病院の生き残り戦略として重要なのが「健康診断」や「
・「結婚してくれてありがとう」「
・私は一馬の父親にこう聞きました。「死亡診断書は青木一馬でいいですか?」父親は少し迷ってから、
「そうですね。地球の名前でお願いします」と微笑みました。
《死亡診断書名 青木一馬 カルテ名 ウルトラマンカズマに変更(変身)》
いいねえ……ニャンコのように亡くなるときは姿を消して亡くなりたいね。超オススメです。(=^・^=)