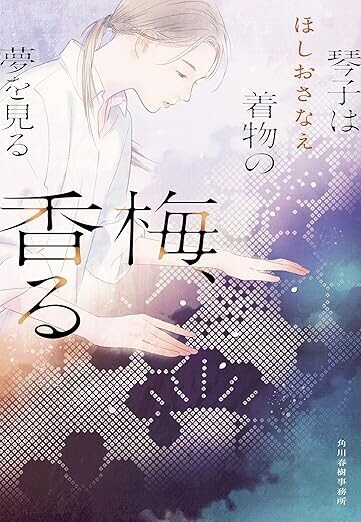
いいなあ。ほしおさなえさん。この間、トークショーに行って、最前列で聞いて、サイン会でサインいただいたけど、気の利いたコトバが出なくて無言だったなあ。(笑)初恋の相手に合ったみたいだったなあ!(笑)(=^・^=)
さて、注目の新シリーズだよー。今回のテーマは着物。
「八王子のリユース着物店「本庄の蔵」で着物査定を担当する本庄琴子は、出張買取のため店主・柿彦の運転する車で、横浜に住む日向菊子の家に向かった。「本庄の蔵では着物についた念を祓ってくれる」という噂が流れており、菊子はそれを聞いて依頼してきたらしい。着物の記憶が見えることを、柿彦以外には誰にも話したことのない琴子だったが、菊子の家で触れた振袖の強い「意志」に、つい……。繊細な手仕事で作られた総絞りの振袖が記憶していた恋の物語。シリーズ第二巻」そのエッセンスを紹介しよう。
・わたしが何度もくりかえしその着物の下で眠り、
・いまの時代、洋服というのはそう長く着るものではない。
人が時間をかけて作ったものだからかもしれない。
人の手で作られた器は何度見ても飽きない。
・かつては完全な分業体制が取られていた。
・「洋服とはなんかちがう。着ているとなにかに守られているみたいで」
「そうなのよ。
・「着物の柄っていうのは、ただきれいなだけじゃなくて、
「むかしからおめでたいと言われてきたものだからね。
・「そうなんですけど、それだけじゃなくて。なんとなく着物には『
「神さま?」驚いて須崎の顔を見た。
「「神さま」は変ですね。でも、単なる『もの』
ているっていうのかな。本庄の蔵にいるせいかもしれませんけど」
・菱刺しって知ってるか?」
「菱刺し?」真子が首を横に振る。
「刺し子の一種だよ。うちの田舎に伝わっているもので、
・「ばあちゃんの作る柄はきれいだったんだよなあ。その振袖も、
オクヤマの言葉で、また真子の胸がどきんとふるえた。
「真子も、きれいだ。着てきてくれて、ありがとう」
オクヤマは遠くを見たままそう言った。
・「ええ。梅のことはわたしもよくわからなかったんです。
・生きていくためには、お金を稼がなければならない。
・「いえ、疲れはありますが、わたしも得るものがあるのです。
主人公の真子は、ワタシと同い年だな、きっと。人には言えない、引きずっている恋があるんだなあ。誰にでも。ジーンとくるなあ……後半は、ウルウル来ちゃいました。このシリーズも長く続いてほしいなあ。超オススメです。(=^・^=)
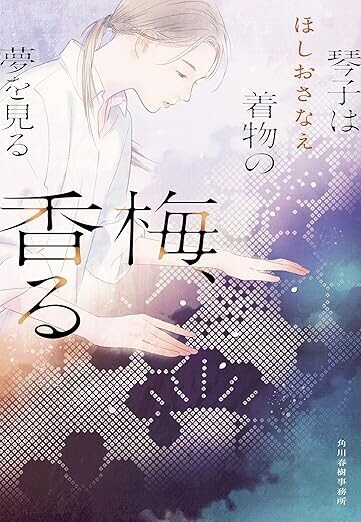
第一弾も併せて読もう。(=^・^=)
